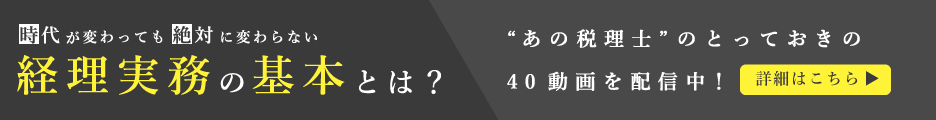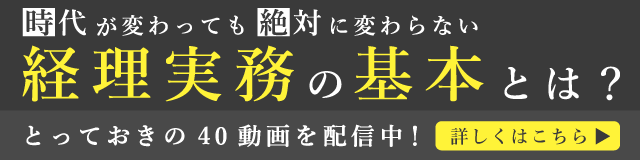「仮払消費税」と「仮受消費税」の差
今回は、消費税の税抜方式による経理処理について確認してみましょう。
ご承知のとおり、日本国内において資産の譲渡や役務(サービス)の提供をした際には、原則として消費税が課税されます。
ただ厳密には、6.3%の国税(消費税)と1.7%の地方税(地方消費税)とで構成されることから、「消費税等」と表現するのが一般的です。
ところで、経理処理には、税抜方式と税込方式とがあり、税抜方式では、いわゆる課税仕入(課税対象である資産・費用等の購入・支払い)を行なったときは、消費税等相当額を「仮払消費税等」とし、反対に売上側では「仮受消費税等」とします。
たとえば108円(税込)の商品を仕入れ、これを324円(税込)で販売した場合、税込方式では「仕入高」108円、「売上高」324円としますが、税抜方式では「仕入高」100円と「仮払消費税等」8円、「売上高」300円と「仮受消費税等」24円とします。
このように、取引の都度「仮払消費税等」や「仮受消費税等」を計上し、最終的にこれらの差が「未払消費税等」となります。
ただし消費税の申告では、課税売上の総額をベースに税額を求め、また計算上、各種端数処理もあり、現実には「仮受消費税等」と「仮払消費税等」の差は納付額と一致しません。
そこで、その不一致分は「雑収入」または「雑損失」とします。
なお、この場合の「雑収入」や「雑損失」は消費税の課税対象でないのはいうまでもありません。
また、前期の確定消費税額が一定額以上である場合には、中間申告および中間納付が必要となります。そして、この場合の中間納付額は「仮払消費税等」とするか、あるいは課税仕入に係る消費税等と区別する意味合いから、あえて別科目、たとえば「仮払税金」とし、または「未払消費税等」のマイナスとして処理することもあります。
○消費税等の中間納付額400,000円を当座預金より支払い、仮払税金として処理しました。
(借方)仮払税金 400,000円
/(貸方)当座預金 400,000円
○決算に際し、消費税等(中間納付額400,000円控除前)が700,000円と確定しました。
なお、仮受消費税等の残高は2,530,500円、仮払消費税等の残高は1,830,392円です。
(借方)仮受消費税等 2,530,500円
/(貸方)仮払消費税等 1,830,392円
仮払税金 400,000円
未払消費税等 300,000円
雑収入 108円
参考:研修出版 経理WOMAN
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
サービス